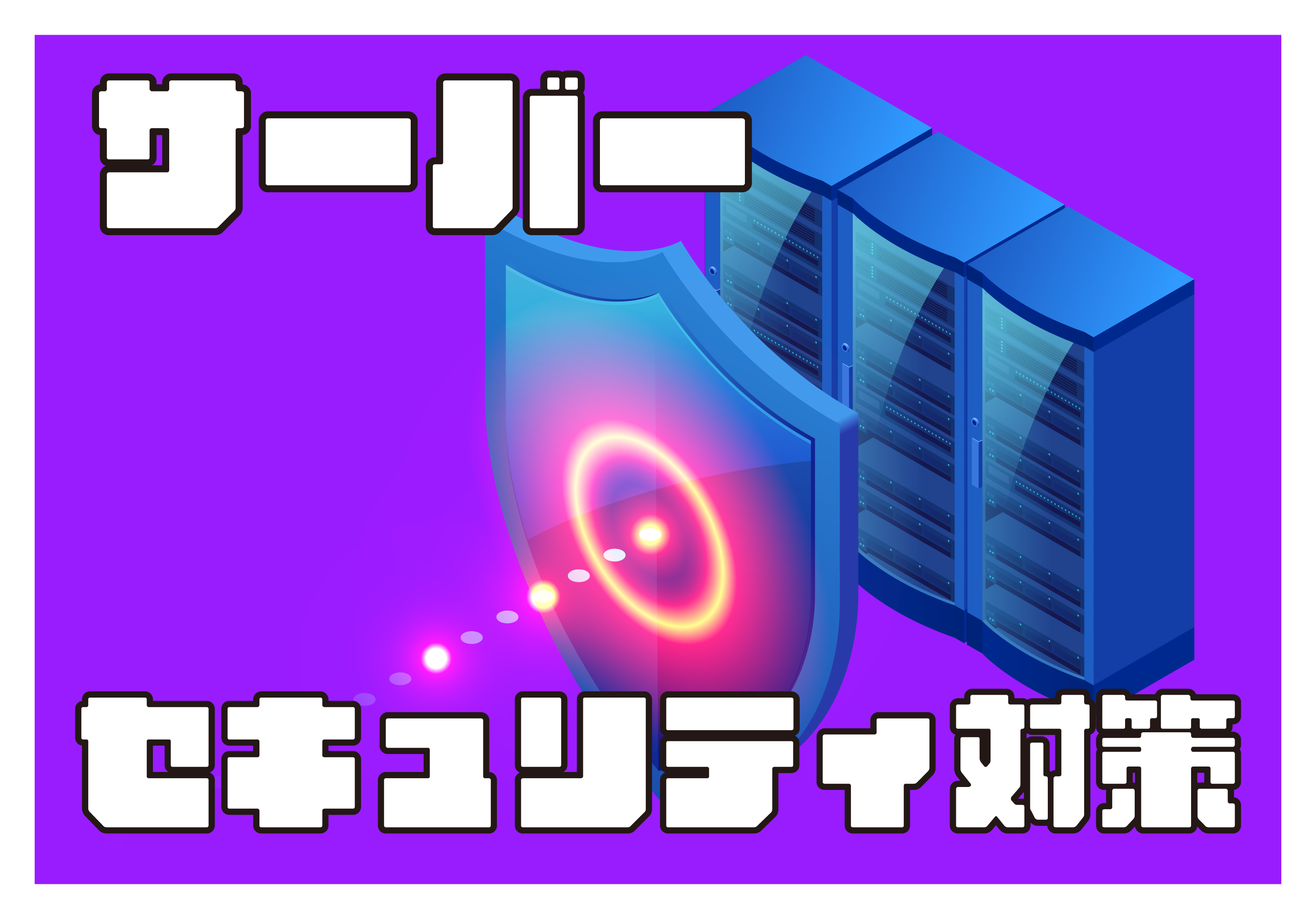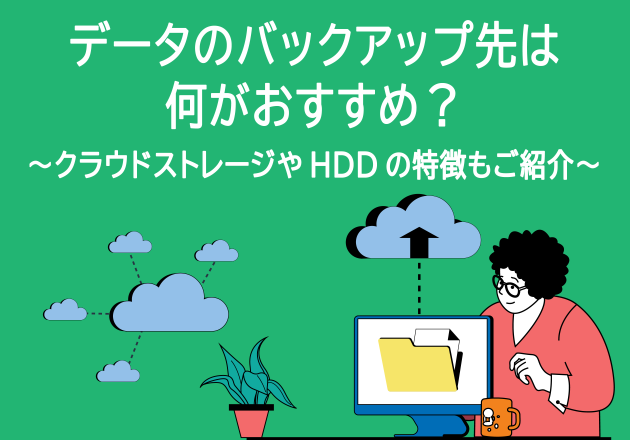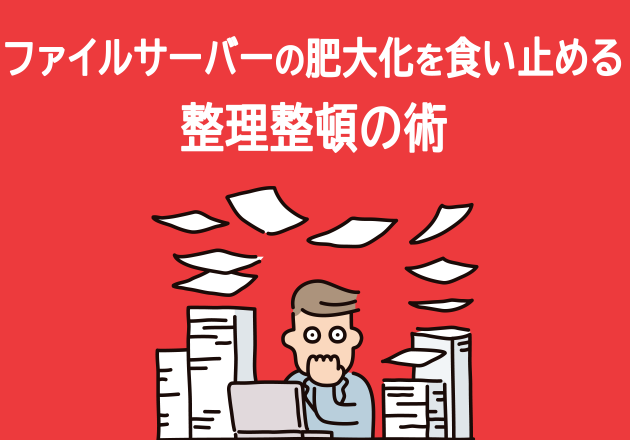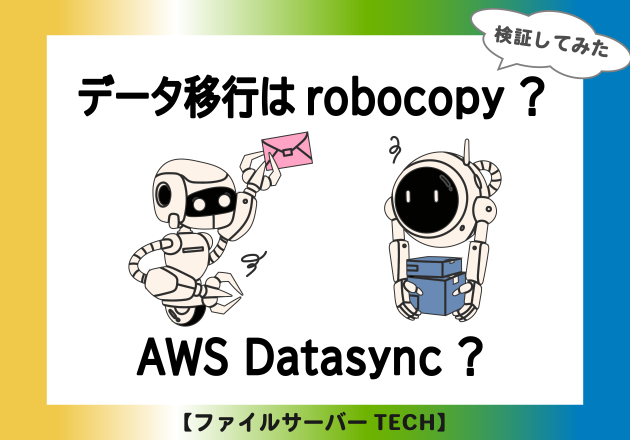|
目次
|
あなたの会社のITインフラは老朽化していないでしょうか。ITインフラの老朽化は業績の悪化にも直結しかねない重要な問題です。しかし、自社のITインフラ管理の老朽化に気づかないケースも少なくありません。
今回は、ITインフラ管理について解説します。コスト削減やセキュリティ管理が簡単になる「クラウド化」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.社内ITインフラ管理とは

社内インフラ管理とは、企業の事業活動の基盤となるインフラを把握・監視することです。一般的にインフラは日々の生活を支える下部構造のことであるため、ITインフラ以外にも電気や水道、オフィス設備も社内インフラに該当。中でも社内におけるITインフラとは、サーバー、データベースなどシステムにおける基盤を表します。
社内ITインフラの管理方法は様々であり、専用ツールを購入して内製する、あるいは管理業務そのものを外注する場合があります。失敗しないためには、キャパシティプランニングが重要です。キャパシティプランニングとは、自社サービス提供のために必要となるハードウェア・ソフトウェアの構成を決めるためのプロセスのことです。企業は利用者数や利用頻度、データの内容をもとに機材の種類や性能、台数、配置などの具体的な計画を作成します。
2.ITインフラ管理が行われる3つの目的

ITインフラの管理は、業務の高速化や効率化を図るために非常に重要です。ITインフラ管理が行われる主な目的として、以下の3つが挙げられます。
【ITインフラ管理の目的】
● 処理性能の向上
● 障害への対応
● コストの最適化
社内インフラを整備する場合、機器やソフトウェアを用意するだけでは不十分です。目的をしっかり把握し、適切に対処することが円滑な企業経営に繋がると言えるでしょう。
①パソコンやサーバーの処理性能の向上
1つ目の目的は、パソコンやサーバーの処理スピードを上げて快適性を確保することです。処理能力が低いと、当然ながら動作は遅くなるため、その分無駄な時間もコストも割くことになり、全体的な生産性が低くなります。
時代が進むにつれ、より大きなデータサイズを取り扱うことや、リアルタイム性を求められる場面も増えています。定期的に機器やサービスの性能を見直すことが重要です。
ユーザー体験に悪影響のないサービス提供を行うためには、システムやネットワークのボトルネックを特定し、適切な対応を行わなければなりません。
②障害への対応
2つ目の目的は障害への対応です。システムには、ネットワーク障害やサーバーダウン、不正アクセスやウィルス感染、情報流出など様々なリスクが想定されます。そのため、障害を未然に防ぐことはITインフラ管理の重要な目的だと言えるでしょう。
リスクを洗い出したら、それぞれに対して適切な対応が必要です。具体的には、重要なシステムの冗長化や監視システムの導入、パソコンやデータの持ち出しに関する社内規則の整備を進めましょう。社内で同じ対応ができるようマニュアル化し、適切な行動が取れる体制を作ってください。
③コストの最適化
3つ目の目的はコストの最適化です。業務の質を落とさず、無駄なコストを削減できるように、継続的な見直しが必要となるでしょう。
例えば、定型業務で時間のかかる作業について、アウトソーシングを活用することでコストを抑えられる可能性があります。また忘れてはいけないのが、古いシステムの保守管理コストの確認です。詳しくは次章で解説します。
3.ITインフラの老朽化は大丈夫?

ITインフラで心配されているのが老朽化です。システム導入当時の担当者が辞めてしまい、5年・10年と使い続けているものの、リプレイスが行われずに老朽化しているシステムも少なくありません。
また、現行のシステムに関する知識がなく、老朽化に気づかないケースも多いです。ここからは、ITインフラの老朽化について、以下の2点を見ていきましょう。
● レガシーシステム
● ITインフラにおけるクラウドサービスの利用
【負の遺産】レガシーシステム
レガシーシステムとは、肥大化・複雑化・ブラックボックス化などの課題を内包する、柔軟性や機動性に欠けた最新技術を適用しにくい古いシステムのことです。また、企業が長期的に利用しているシステムでもあります。業界内でレガシーシステムは負の遺産とも呼ばれており、本来であれば改善が求められるものです。
しかし、レガシー化するシステムは、そもそも企業が長期的に利用しているシステムであり、業務と密着的に関わっています。システムの改良や置き換えは難しく、運用・保守のコストが高いことが大きな問題。また、レガシーシステムへの対応を誤るとDXの実現の妨げになり、2025年以降において最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性があります。レガシーシステムの対応を2025年にどう乗り切るかは喫緊の課題となっており、このことが「2025年の壁」と言われているのです。
【リスク対策】ITインフラにおけるクラウドサービスの利用
ITインフラ老朽化に対するリスク回避の方法として、クラウドサービスの利用が挙げられます。
クラウドサービスであればそもそもサーバーなどの物理資産を持たなくて済むだけでなく、責任範囲の軽減が可能なことにより、ITインフラ老朽化についてリスク対策を取ることが可能です。また、ローコード開発ツールや資産管理ツール等、様々な管理ツールのクラウドサービスも普及し始めています。
これらのことから、ITインフラだけでなく、その管理にクラウドサービスを利用することで、資産の老朽化対策と業務の効率化が実現できる可能性があります。
4.これまで主流だったITインフラとの違いは?

採用するサーバーによって作業効率やコストは大きく変化するため、自社にとって適切な導入方法を採用していかなくてはなりません。今回は2つの運用形態についてご紹介します。
【サーバーの種類】
● オンプレミス
● クラウド
それぞれついて詳しく見ていきましょう。
オンプレミスとは
今まで多くの企業が、オンプレミスでシステムを管理・運用してきました。オンプレミスとは、自社でソフトウェアや機器を保有・管理する利用形態や運用形態のことを指します。
オンプレミスの課題は、ハードウェアを調達したり設置スペースが必要になったりする点。サーバーリプレイスや運用管理費もかかります。さらに、サーバーリプレイスを行うと数カ月~数年かかる場合やサーバーの故障などで買い替える場合、調達リードタイムを再度要してしまいます。
クラウド
クラウド(クラウド・コンピューティング)とは、インターネットなどのネットワーク経由でインフラ機能やサービスを提供する形態のことです。ユーザーは資産を保有する必要がなく、必要な時、必要な分だけ利用することが可能です。
クラウドのメリット・デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
【メリット】
● 利用開始までのスピードが早い
● 初期費用が不要
● 運用・保守管理が不要
【デメリット】
● ネット環境が必須
● サービス終了のリスクがある
インターネットを介してクラウドコンピューティングサービスを利用することで、すぐにサーバーが利用可能です。調達リードタイムが長いオンプレミスと比較すると、スピーディーで手軽に利用できることが最大のメリットだと言えるでしょう。
5.近年のITインフラ管理の課題

前章では、オンプレミスとクラウドという2種類の運用形態について解説しました。本章では、近年のインフラ管理における課題、マルチベンダー化についてご紹介します。
マルチベンダー化
マルチベンダー化とは、異なるベンダーの製品やサービスを組み合わせて使用する仕組みのことです。
昔は、一つのベンダーからシステム一式を購入していましたが、これには購買先やサポート窓口を一元化できるメリットがありました。しかし、開発方針に合わせて製品を選択でき、多彩なサービスを望むように組み合わせられることから、マルチベンダー化がユーザーから好まれるようになりました。
結果として窓口が複数になったり、責任範囲がメーカーによって異なることでグレーゾーンが生まれてしまったりすることに注意が必要です。
6.パブリッククラウド

パブリッククラウドとは、不特定多数のユーザーに対し、インターネットを介してサーバーやソフトウェア、アプリケーションを提供するサービスのこと。パブリッククラウドサービスの多くは初期費用が無料で、導入コストをかけずに必要な時に必要なだけITリソースを利用できる点が最大のメリットです。
代表的なパブリッククラウドとして、以下の3つが挙げられます。
【パブリッククラウド】
● Amazon Web Service(AWS)
● Microsoft Azure
● Google Cloud Platform(GCP)などがある
ここでは、AWSにフォーカスし、パブリッククラウドの特徴をご紹介します。
【AWS】Amazon Web Servicesとは?
AWSとは、Amazon Web Servicesの略でAmazonが提供する複数のパブリッククラウドのこと。ハードウェア・ソフトウェアを購入する必要はなく、常に最新のセキュリティが利用できます。また、CPU・メモリ・ストレージ容量などの拡張が簡単なこともメリットの1つです。
システムインフラ環境の保守・セキュリティ対策は事業者であるAWSが担当してくれるため、ユーザーは安心して利用できます。
一方、ユーザーはゲストOS・ミドルウェア・アプリケーションや、構築したシステムに関するセキュリティを担当します。自社にAWSを導入することで、ハードウェアにまつわる管理やリスクからの解放、利用量に応じた従量課金によるコスト削減、システム管理者の負担軽減による人的リソースの有効活用が見込めます。
7.【マルチクラウド】が選ばれる傾向に

現在、企業の情報システム環境の主流となっているのがマルチクラウド。マルチクラウドとは、複数のクラウドサービスを組み合わせることにより、企業にとって最適な環境を構成する運用形態のことです。
これには、クラウド毎の得意分野を組み合わせることや、一つのサービスに依存する危険性を減らすという目的があります。マルチベンダーと似ていますよね。マルチクラウド化の流れは今後より一層進んでいくものと考えられます。
8.まとめ
今回は、ITインフラ管理について解説しました。
ITインフラ管理を適切に行うことは、企業の発展に関わる大切な課題です。これまで見てきた通り、インフラ環境をクラウド化することで、システムの老朽化や設備費用の問題が解消され、時代に合わせたサービス展開が可能となります。しかし、ITインフラの構成要素には多くの選択肢があります。様々なサービスの中から自社に合うものを選び、導入することが大切です。
クラウドサービスを導入したいと思いながらも、「サービスが複雑・大量にあって良く分からない」「セキュリティが心配」「費用面が心配」というような不安を感じるお客様もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、弊社の「AWS移行サービス」「AWS設計・構築サービス」をご利用ください。弊社はAWSに精通したエンジニアが多数在籍しており、お客様の課題をヒアリングの上でクラウド導入に向けてサポート致します。是非お気軽にお問い合わせください。
クロス・ヘッド関連サービス
※Cloud Compassはクロス・ヘッド㈱が運営するクラウドサービスです。